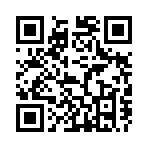2010年02月03日
新幹線安全神話

1/29日に起きた停電による新幹線不通事故は、保守作業でパンタグラフ部品のボルトを締め忘れ、それが架線を引きちぎったことによる停電であったことが発表されました。
西日本新聞2010.2.2
事故直後、1/31 に、新幹線の安全性を書き並べていましたが、今回の事故はシステム上の問題ではないとはいえ、安全神話を覆す事故に繋がりかねない危うさを含んでいたみたいです。
ところで、パンタグラフの架線と接する部分はここにも書いてあるとおり、「すり板」ですが、架線と接触しながら走行するわけですから、雨垂れが石をうがつように一箇所が常に摺れ続けるとくぼみは深くなり、早晩真っ二つになってしまうと思われませんか?
もちろんそれを防ぐために定期的に「すり板」は交換されていますが、架線を一箇所だけで摺り続けない工夫がなされているということを聞きました。
それは、架線が支柱から支柱へ張り渡される際に、空中から見ると(地上から上を見ても同じですが)「く」の字を描くように張られているというんです。
そうすれば「すり板」の側からいうと、電車の走行につれて架線が「すり板」の上を右から左、左から右と、決して常に一箇所を摺ることがないように配慮されているというわけです。
機械で巻かれたミシンの糸が送られる際に糸巻きに直角に見ると、糸は左右に平行移動しているように見えるのと同じ理屈です。