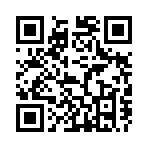2009年10月22日
シルバーとブレイキー
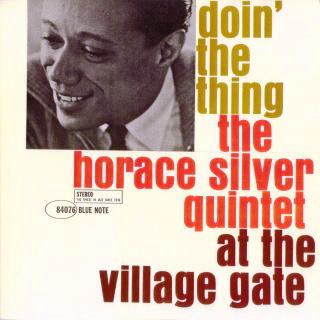
ジャズメッセンジャーズと聞いて、皆さんは、アート・ブレイキー、ホレス・シルバーどちらを思い浮かべられるでしょうか。
-西日本新聞2009.10.17夕-にあるとおり、
カフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズ Vol.1(Blue Note・1507)、
ホレス・シルヴァー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ(Blue Note・1518)とリーダー名は違っても、
ケニー・ドーハム(tp)、ハンク・モブレー (ts) 、ホレス・シルバー(p)、ダグ・ワトキンス(b)、アート・ブレイキー(ds)というメンバーはまったく一緒です。
ホレスシルバークインテットになってからの私のベスト盤は、同意見の ページ もあり心強いところですが“ドゥーイン・ザ・シング”なんです。
メンバーは、その前のすべて大御所というところから次のとおりヤヤ軽い“名前”に変わっていますが、騒々しさは抜群です。
ホレス・シルヴァー (p) 、ブルー・ミッチェル (tp) 、ジュニア・クック (ts) 、ジーン・テイラー (b) 、ロイ・ブルックス (ds)
文字列を赤く目立たせたジャケットデザインは、なぜか「カフェ・ボヘミアの・・・」と似通っていますね。





2009年08月09日
両雄並び立つ
 両雄並び立つジャズ盤・4枚が掲載されていました。 -西日本新聞2009.8.8夕-
両雄並び立つジャズ盤・4枚が掲載されていました。 -西日本新聞2009.8.8夕-私の守備範囲ではない、チック・コリア&ハービー・ハンコック(新しすぎる)、デューク・エリントン&カウント・ベイシー(古すぎる)、リー・リトナー&ラリー・カールトンの3枚は論外としても、スタン・ゲッツ&J・J・ジョンソンのオペラハウス盤は触手が動かないこともありません。
でも、ゲッツ、マリガンはやはりチェイサーでしかなく、ギムレットにはなりきれない感じです。
※R・チャンドラーが書いている「ギムレットには早すぎる」とは
“両雄並び立つ”、両雄がインスパイアーし合ったお気に入りを私なりに選んでみました。
まず、ハード・バップを完成させたともいえる「ジャイアント・ステップス('59年)」で颯爽と登場する J・コルトレーンが、一月後に代表作「サキソフォン・コロッサス」をレコーディングするS・ロリンズと競演した、「テナー・マッドネス(Tenor Madness) 」('56年)。
後にアルトサックスと“見まがう”音色(M・デイヴィスクインテットでのC・アダリーとの相似)に変化する前のコルトレーンは、ここではロリンズと“見まがう”音色です。
続いて、O・ピーターソン&M・ジャクソンの「ベリー・トール(VERY TALL)」('61年)です。
MJQでは十分にインプロビゼーションが生かされてないと言われ続けていた、M・ジャクソンが、J・ルイスの非スイングから解放されて云々との評もありましたが、私はここでのジャクソンが大いに好みでありながら、MJQ枠でのジャクソンも同じくらいに好みでもあります。
最後は、W・ケリー&W・モンゴメリーの「ハーフ・ノートのW・MとW・Kトリオ(SMOKIN' AT THE HALF NOTE)」('65年)。
この盤は、言葉にするのがばかばかしいほどの、スイング・アドリブ・インスパイアの塊で、聴き終わるとすぐにまた針を戻したく(LP盤はこう表現しますね)なるとともに、どっと疲れもでるとほど厄介な1枚でもあります。

2009年07月31日
COMBO閉店
 福岡ジャズ喫茶の草分け「COMBO」が閉店するという記事が載りました。
福岡ジャズ喫茶の草分け「COMBO」が閉店するという記事が載りました。―西日本新聞2009.7.28(夕)―
文中「COMBO」が'64年に開店した「福岡で初のジャズ喫茶」とあるのは間違いだと、古き時代のジャズきちがい(失礼)に教えていただきました。
少なくとも‘62年には昔の玉屋裏・博多川の並び2・3軒上流に、その名も「リバーサイド」というジャズ喫茶が存在したそうです。
「リバーサイド」にはタモリや洋輔など有名どころは縁がなかったのかもしれませんが、九大出身のハードボイルド直木賞作家・原尞(はら りょう=寮のウ冠を取った字)が高校時代に入り浸ったという店だそうです。
昔、原尞が新聞に寄せたエッセイが こちら に集録されています。
実はこのエッセイ、本ブログでも前に紹介していましたが。
このジャズきちがいさんが、'63年に大学を卒業し東京へ出る前だから'62年暮か、63年初頭に撮ったものだと、リバーサイド店内の 写真 を見せてくださいました。
※店の形態は変わっていながら、「リバーサイド」そのものは現在も存在しているようです。
九州のジャズ喫茶マッチ

2008年12月18日
ウインター・リーヴス
 オータム・リーヴス、秋を過ぎて、「枯葉」のディスクが取り上げられていました。 -西日本新聞2008.12.13(夕)-
オータム・リーヴス、秋を過ぎて、「枯葉」のディスクが取り上げられていました。 -西日本新聞2008.12.13(夕)-キャノンボール・アダレイのリーダーアルバムでありながら、必ずといっていいほど、“マイルス”の「サムシンエルス(somethin' elseだから)」と言われるこのディスク。
ここに書かれているように、他ではこの盤のキャノンボールをよい出来だと言っているのを見たことがありませんし、私もそんなに聴きたいとは思えませんが。
ビル・エヴァンス、この「ポートレイト・イン・ジャズ」にくわえて、「エクスプロレイションズ」・「ワルツ・フォー・デビイ」・「サンディ・アット・ザ・ビレッジ・バンガード」の4作は、“リバーサイド四部作”と称されていますよね。
ウイントン・ケリーが入る前、しばらくの間マイルス・デイヴィスとの共演の後のこの頃は、エヴァンスらしくなくスイングし、ヴィヴィッドな乗りで、黒人一辺倒の私でさえ
“LP”を持っているほどです。
ヴォーカル嫌いな私にサラ・ヴォーンはあまりお呼びではありませんし、ジム・ホール、ロン・カーターでは物足りません。
「アローン・トゥゲザー」といえば、ジャズ評論家?の誰だったか失念しましたが、「二人ぼっち」なる名訳がありました。
まあジャズも落語と同じで、『何を聴くか』より『誰を聴くか』が大きいと言えます。
2008年10月05日
東京JAZZ2008
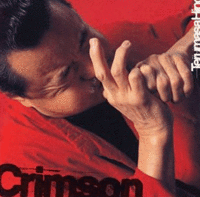 一週間ばかり前でしたかNHK・BSで、東京国際フォーラムで開催された“東京ジャズ2008”が放映されていました。
一週間ばかり前でしたかNHK・BSで、東京国際フォーラムで開催された“東京ジャズ2008”が放映されていました。だけどまあ、今のジャズって本当にスイングしなくなりましたね。
飛ぶ鳥落とす勢いの上原ひろみにしても、イマジネーション・インプロビゼーションの素晴らしさは(未熟な私にも)僅かにはわかりますが、“スイング”となると、ハードバップからは異質だった、マッコイ・タイナーのほうがまだスイングしています。
It Don't Mean A Thing (スイングしなけりゃ意味ない)と言っていたデューク・エリントンもこれほどまでにスイングしない曲がジャズとして演奏されるとは思いもよらなかったことでしょう。
それにしても日野皓正のホッペの膨らみはさらに進化したように見えました。
ディージー・ガレスピーは膨らませすぎで明らかに頬にタルミが見えましたが、今のところ大丈夫そうな日野皓正の今後が少々心配です。
代わりに首を膨らませていたマイルスが頬のたるみなく、老いを感じさせなかったのが印象的です。
(何日か前に書いたように、マイルスは私に容貌でではなく音楽の方向で老いを印象づけました)
2008年09月28日
まだマイルス礼賛ですか?
1960年代前半以降、つまり、スイングするピアノ(レッド・ガーランド、ビル・エヴァンス、ウイントン・ケリー)が去って後、さらに晩年のマイルスを未だに評価する人を私は信用しません。
マイルスは、サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム辺りまででしょう。この頃の、頂点に達したスマート、リリシズムもいいのですが、やはり落語と同じように何度も繰り返しの“聴”に耐え続けるベストアルバムは「バグズ・グルーブ」で、しかもその中の同名曲・take 1 でしょう。
ミュージシャンが新しい方向を目指すとき、ともすれば評論家は、たとえ自分が楽しめる音楽でなくとも、その思想についていけていることを示さんが為、無理やり高い評価をし勝ちだという印象を受けます。
いわゆるシーツ・オブ・サウンド以降のコルトレーンもやはり暫くは、新しい奏法の探求者としてスイングをなくした(歌を忘れた)カナリヤであるにも拘らず、評論家と称する人から一様に高い評価を受けました。
でも、死後40年を経た今日、フリー・ジャズに傾倒して以降のコルトレーンは手の平を返したように、見向きもされなくなり、当時のもてはやし方はどうした、と言いたくなります。そのうちマイルスも同じ運命を辿るものと思います。
ここのコメントの主・小栗勘太郎は、音楽“愛好家”とあり、“評論家”とは書かれていませんので、個人的な好嫌の範疇ということで、ムキにならないでおきましょう。
2008年02月17日
演歌の心にジャズは入り込めません
 天が二物を与えたとして、ナット・キングコールと美空ひばりの記事が西日本新聞2008.2.16夕刊に掲載されていました。
天が二物を与えたとして、ナット・キングコールと美空ひばりの記事が西日本新聞2008.2.16夕刊に掲載されていました。二物とは、前者にはピアノ演奏と歌声、後者には演歌(の心)とジャズ(の心)というわけです。
ここでは小栗勘太郎が、ひばりの、ナット・キングコールトリビュート盤をとりあげ、天はひばりに一物目の演歌のみでなく、二物目のジャズの歌唱力をも与えたと、まさに絶賛しています。
しかし私にとって、「ジャズにおいても一流」とはどこを取って言い得るのかまったく分りません。
人口に膾炙(かいしゃ)している「真赤な太陽」を聴いてどこにもジャズのノリはないように、ひばりにジャズのノリがないのは当たり前で、演歌のノリとジャズのノリ、両方を完璧に持つなどありえないんです。
演歌歌手に少しでもジャズののりを求めるとすれば、八代亜紀のほうにその資質はあります。
男性でいうと、森進一にはあって、五木ひろしにはありません。
ここで取り上げられている、ナット・キングコールは(ジャズの)ノリのよさでは最高の歌手だと私も思いますが、このノリにひばりが追従できる訳がないんです。
ひばり礼賛もここにいたると、「裸の王様」然で、談志・たけしを“他人(ヒト)に負けないように”礼賛するのとおなじ、いわば強迫観念とでもいえそうで気持悪いばかりです。
2008年02月13日
鞴(ふいご)とFUEGO
 クールストラッチン(COOL STRUTTIN')・ケリーブルー(KELLY BLUE)・フエゴ(FUEGO)は、どれが一番ファンキーなのかあらためて聴き比べて見ようとLP・CDを取り出して、面白いことに気付きました。
クールストラッチン(COOL STRUTTIN')・ケリーブルー(KELLY BLUE)・フエゴ(FUEGO)は、どれが一番ファンキーなのかあらためて聴き比べて見ようとLP・CDを取り出して、面白いことに気付きました。私の小学生時代(終戦直後)、小学唱歌に 村の鍛冶屋 というのがありました。 今はもうなくなっているんでしょうか。
歌詞に「・・・鞴(ふいご)の風さえ・・・」とあります。
鞴を索くと、
ふいご 【鞴/吹子】
〔「ふきがわ(吹革)」から転じた「ふいごう」の転〕金属の精錬・加工に用いる火をおこすための送風器。
獣皮を縫い合わせた革袋などに始まり、次第に改良された。
気密性の箱の中のピストンを往復させて風を送り出すもの、風琴に似た構造をもつものなどがある。
足で踏む大型のものは踏鞴(たたら)と呼ばれる。ふき。ふきがわ。
とありました。
(ここの“たたら”と、“たたらを踏む”との関係にまた興味がいきますが、これは置いといて)
先のドナルド・バードの「FUEGO」については、LPジャケットの解説に、
“fuego(フュエゴ)”とは、スペイン語で炎のことを意味する、とあります。
鍛冶屋などが使っていた、火に風を送り込む装置を、スペイン語のフュエゴからとって、鞴という字を当てたんでしょうか。
妙なことに引っ掛かってしまい今日はジャズは聴かずじまいでした。
2007年12月26日
オスカー・ピーターソン
 西日本新聞・12/25夕刊[ニューヨーク24日共同]によりますと、オスカー・ピーターソンが23日夜亡くなったそうです。
西日本新聞・12/25夕刊[ニューヨーク24日共同]によりますと、オスカー・ピーターソンが23日夜亡くなったそうです。1953~63年、約10年間の演奏しか興味がなかった私でも、オスカー・ピーターソンとMJQだけは別でした。
レーザーディスクで映像も見られることもあって、J.A.T.P. '83 LIVE IN JAPAN 「OSCAR PETERSON BIG4」は、今でも愛聴盤です。
オスカー・ピーターソンに限らず、バラードがきらいな私は、このフェイヴァリット・ワンの評価に賛成です。
記憶違いでなければ、ミルト・ジャクソンとのこのアルバム「VERY TALL」・“Reunion Blues”のソロで、フレーズの一音が少し引っ掛かって、すぐにもう一度同じフレーズを今度は完璧に弾き直している個所があります。
1993年脳梗塞で倒れ、復帰後、2003年来日公演の際には、2ちゃんねるでも相当喧しかったようです。
最後の来日はこの1年後、2004年10月だったとか。
終戦後、初来日の時には、物資の貧弱な日本の椅子がこの巨体を支えきれずに壊れたと、語り継がれています。
2007年09月05日
昭和のジャズ喫茶・リバーサイド
 ジャズスポットといえば、昭和3・40年代にはマニアのたまり場として、名門レーベルの名を冠した、「リバーサイド」というジャズ喫茶(その名も懐かしいLPレコードを聴かせるだけのサービス付喫茶店)が、今はなき玉屋デパートの並び2・3軒南にありました。
ジャズスポットといえば、昭和3・40年代にはマニアのたまり場として、名門レーベルの名を冠した、「リバーサイド」というジャズ喫茶(その名も懐かしいLPレコードを聴かせるだけのサービス付喫茶店)が、今はなき玉屋デパートの並び2・3軒南にありました。-博多川河畔に位置するので「リバーサイド」と名付けたのだと思いますが、実は現存-
この「リバーサイド」について、九州大学/文学部/美学出身・直木賞作家、原尞(この文字は皆さんのブラウザで正しく表示されていますか? 寮のウ冠を取ったものですよ)がずいぶん昔、西日本新聞だったかに連載していたエッセイを引っ張り出し下に紹介してみました。
エッセイ
2007年09月05日
旧福岡ブルーノート
 「ビルボードライブ福岡」として生まれ変わった、「福岡ブルーノート(開業時「ブルーノートフクオカ」)」、2年前、最終営業日の模様を伝えるスクラップがありましたので、ご紹介します。
「ビルボードライブ福岡」として生まれ変わった、「福岡ブルーノート(開業時「ブルーノートフクオカ」)」、2年前、最終営業日の模様を伝えるスクラップがありましたので、ご紹介します。新聞記事
この時点で既にジャズではありませんでした。
2007年09月04日
無節操に堕落したブルーノート
終戦後、洋楽に飢えていた時代、極東放送(FEN=Far East Network)にラジオのチューナーを廻し、流れるビルボードのトップ10だったか20だったかを楽しんだ若い頃もありましたが、今では、「ハードバップ」以外はジャズ、果ては音楽じゃないというアブノーマルな身となっては、このライブハウスのリニューアルも、「ふ~ん」でしかありません。